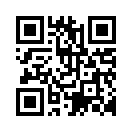2022年12月26日
忙しくも希望に満ちた、夜だった
こんな窮屈な時代なんですけど、
キャラクターとテクニックさえあれば、
毒舌漫才もまだまだ受け入れられるという
「夢」を感じました。
それはそれは、
大変な夜だった。
テレビ離れと言われて久しい昨今、
この12月18日だけは、別格だった気がする。
「鎌倉殿の13人」と、
「M-1グランプル」のダブルヘッダー。
ユーマーズに言わせれば「どちらでもいいこと」だが、
ちょっと深く手を伸ばせば、
遠い遠い糸でこの2つは、
ユーマーズの想いとつながっている。
今年、
「勇魔(UMA)殿の13人」と銘打って、
ユーマーズの今をここに結び付けていた。
とりわけ、
尼将軍の名演説と、
最終回の13分間の妙演は、
未だにその余韻を残している。
13人とは、
鎌倉殿を支えた13人であると同時に、
熾烈な権力闘争に、鎌倉存続と銘打って
討ち果たされ失われた13の魂でもあった。
人は、戦い、生き、
やがて朽ちる。
それまでの、人でしか描けない、
唯一無二のストーリーこそが、
その肉体に「生を吹きかける」ことであり、
同時にユーマーズが織り成す劇場そのものとなっている。
イギリスの大哲学者、
バートランド・ラッセルは、
名著『幸福論』の中でこう述べている。
退屈とは、
事件が起こることを望む気持ちが
《くじかれた》ものである。
(暇と退屈の倫理学 國分巧一郎著)
この論理に沿えば、
退屈ではない状態、
いわばやりがいに充満している状態とは、
絶えず何かが起こり、
そのことが取りあげられ、
期待通りに展開するスリリングな日常、
と私は意訳している。
ユーマーズが、
劇場に一歩でも近づけようとする真意は、
実はここにある。
退屈の反対は快楽ではない。
興奮なのだとも説いている。
そうみれば、
嗚呼、北条義時の人生は、
興奮に充満した生涯であったばかりか、
後世の私たちが解釈する彼の人生を、
単に「かわいそうだ」の五文字では到底語れまい。
時代に逆行する毒舌漫才。
何でもコンプライアンス、
何でも3密禁止でウットオシイ。
そんな安全で無難で平坦な世の中に、
まるで様変わりしたここ最近の鬱積を、
ウエストランドは「ネタ」で、
「笑い」で、打ち砕いた。
冒頭のコメントは、
M-1審査員を務めた松本人志氏の、
表彰後のコメントである。
毒舌に「夢」を覚える時代である。
それくらい、日常に「奔放さ」を封じてきた。
そんな平らな生活を甘んじて受け続けている、
誰あろうワタシタチのジレンマもまた、際立つ。
発言に思慮を重ね、
整ったまん丸い言葉たちが、
交差点を徘徊する。
誠実さの成せる業であり、
生きるという意義を削いだ末路でもある。
壮絶な人生を駆け抜けた北条義時、
壮絶な勝ち抜き戦の末、
頂に立ったウエストランド。
どれも、
ユーマーズが目指す生き様、
その大きなビジョンと
だぶって見えた。
果たして北条義時の人生というものは、
晩年、妻と親友に毒を盛られ、
実姉の北条政子に見殺しにされるという
無残な末路を生きた物語だったのだろうか。
果たしてウエストランドの漫才というものは、
単に過激で横柄な漫才でもって、
世の中に浅い笑いを振りまこうという、
そんな容易い意図に寄せたものだったのだろうか。
否、当然の、否だ。
どれも意味に満ちている。
劇場を謳歌している。
先日、大学内で襲われた社会学者の宮台真司氏は、
復帰後のライブ配信で、
「クソ社会に生きるクズ共」という
強烈な言葉を表題にしつつ、こう言っている。
いざという危機の状態になった時に、
本当に助けてくれるという事を
知る事が大事だ。
最後は仲間だ。
グランドで共に生きた戦士たちの、
同志との絆が最後との砦となり得る。
SNSのいいねボタンが増えたとて、
さてどれくらいのいいねを「仲間」と呼べるだろうか。
その危うさが、まさに今のつながりの課題でもある。
だから、ユーマーズ劇場が必要だとも言えはしないか。
その証左を見た気がした。
何度でも言う、
だから、
ユーマーズが、出番なのだ。
そこに、
ここにしかない、
「夢」が現れる。
「窮屈な時代」への風穴が、
やがて、こじ開けられる。
単にグランドを駆け、
ボールを投げるそのも一つ深いところで、
そんな「夢」が、劇場という馬車を使って、
今日もグランドに、砂煙を立てている。
ズッコケたっていい。
お尻の砂を払って、
また立てばいいだけだ。
そんな思いに立てばこそ、
2023年もまた、
貴方にしかない、
充満した劇場を展開することができるだろう。
それはそれは、
大変な夜だった12月18日は、
ユーマーズの未来が見えた、
忙しくも希望に満ちた、夜だった。